一絃琴発祥の地「須磨」に伝わる伝統の調べ
名称
須磨琴は一枚の板に一本の絃を張っただけの、きわめて簡単、原始的な小琴である。
古いものは、板の厚さも均一で、現行のものは胴板の裏をくって共鳴を計っているが、 いずれにせよ、本格的な共鳴装置を持たないので、音量が小さく、清華で素朴な音を発する。須磨琴、一絃琴、板琴、独絃琴、ひとつ緒の琴、などの呼び名がある。
形
全体の形はおそらく七絃琴を模したものと思われるが、角型の一端から始まって、 次第細そりに丸型の他端で終わり、その途中、両側の二ヶ所づつに半楕円形のくり込みがある。角型の広い方の端を龍頭といい、丸く狭い方の端を龍尾と呼ぶが、全体として龍の形を連想させる。
規格は必ずしも一定しないが、須磨寺所蔵の覚峰作の最古の一絃琴では、 厚さ一・三センチ、長さ一一三センチ、幅は龍頭部で一二センチ、龍尾部で八センチ、 くり込み部で七センチ(いずれも概測数)となっており、他の琴も概ねこれと似た数値を示す。中には一年の日数に準じて、長さを三尺六寸六分に定めたものもある。
右に述べた七絃琴と同形のものを分類上「行平型」といい、これが最も一般的であるが、 このほかに「太橆型」と称して、側部にくり込みがなく、龍頭部の両側をくり込んでいるものがある。
わが一絃須磨琴保存会(以下、本会と称す)では、いわば「折衷型」として、行平型に準じつつ、くり込みのきわめて浅いもの、又はくり込みの全くないものを用いることにしている。
構造と材質
龍頭の端近くに糸を通す孔があって、これを龍眼といい、龍尾の端近くに糸巻すなわち転軫を立てる孔があって龍孔と呼ぶ。 山繭の絹糸で作った絃(昔は三絃や琵琶の絃を転用したこともあった)を龍眼から裏へ通して横木で止め、他の端を転軫に巻き、龍眼の近くに駒すなわち琴柱を置いて絃を浮かす。転軫は紫檀、黒檀などの堅い木を用い、琴柱には、竹、象牙、角、白檀のほか、桃の核なども用い、形は半月形や富士形にすることが多い。
胴は、古くは杉板や竹が用いられたが、今は専ら桐材で、木地のままか、焦げ色をつけ、その表面に音階を示す露(徽ともいう)を置く。露は音階に応じて十二箇又は十三箇が普通で、象牙、珊瑚、鈿螺、などで作り、小さな丸型が多く、時に千鳥型に刻むこともある。
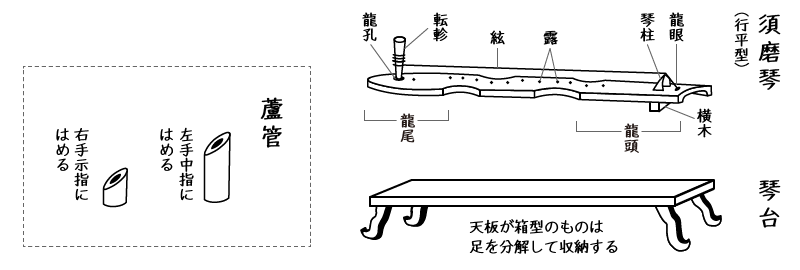
奏法

昔は琴をそのまま膝の上にのせて弾いたといわれ、そのような古図も残っているが、今は四つ足の琴台に載せる。時には足の長い琴台を用いて立奏する。
弾奏に際して、奏者は琴の龍頭を右に、龍尾を左にして琴に向かい、中央より稍々龍頭寄りに正座する。次いで、象牙または角製、牛骨製(昔は竹製)で、一端を斜めに切った長短二つの蘆管を指にはめる。その大きさは直径が約二・五センチ、短い方で長さが約三センチ~四センチ長い方で四センチ~五センチであるが、その短い方を右手の第二指に、長い方を左手の第三指にはめる。
いよいよ演奏の開始に当っては、まず、右手の蘆管で琴柱に近い部分をはじきつつ、左手で糸巻きを回して弦の調律を行う。開絃の音を望む調子に合わせるのである。調律が終ると、左手の蘆管で糸の勘どころを軽く押えながら、右手の蘆管で絃を前または後ろへ弾いて、旋律を作り出すのである。左手の蘆管で絃を摩擦したり、琴板を叩いたり、琴板に手圧を加えて音に変化を与えるような特殊な技法を用いる場合もある。
音階は、開絃を0とし、勘どころは一から十二まであって、琴面の露で示されているが、もちろん、実際の演奏では半音も用いるし、十二音階とは限らない。多くの曲目はいわゆる弾き歌いで、弾きながら歌うのである。
曲種
明治期までに出版された譜本に、真鍋豊平の「須磨の枝折」、徳弘太橆の「清虚洞一絃琴譜」、島田勝子の「一絃琴正曲譜本」などがあり、これらに採録されたものが現在の段階では古典曲と考えられるが、そういう古典曲は約五十曲である。そのうち「今様」「須磨」などが古伝の曲とされているが、大多数が嘉永以後の作で、真鍋豊平の作が最も多い。歌材は古い文学作品によるものが多く、特に古今和歌集や万葉集に依拠したものが少なくない。これらの古典曲の中には、いわゆる外曲と称して、他の邦楽から移したものも含まれるが、大多数は一絃琴独自の曲である。
古典曲のほかに、もちろん、新曲もあるが、本会独自で創作したものは別として、一応、師伝として本会が伝習した曲目は新古合わせて百余曲に達している。
